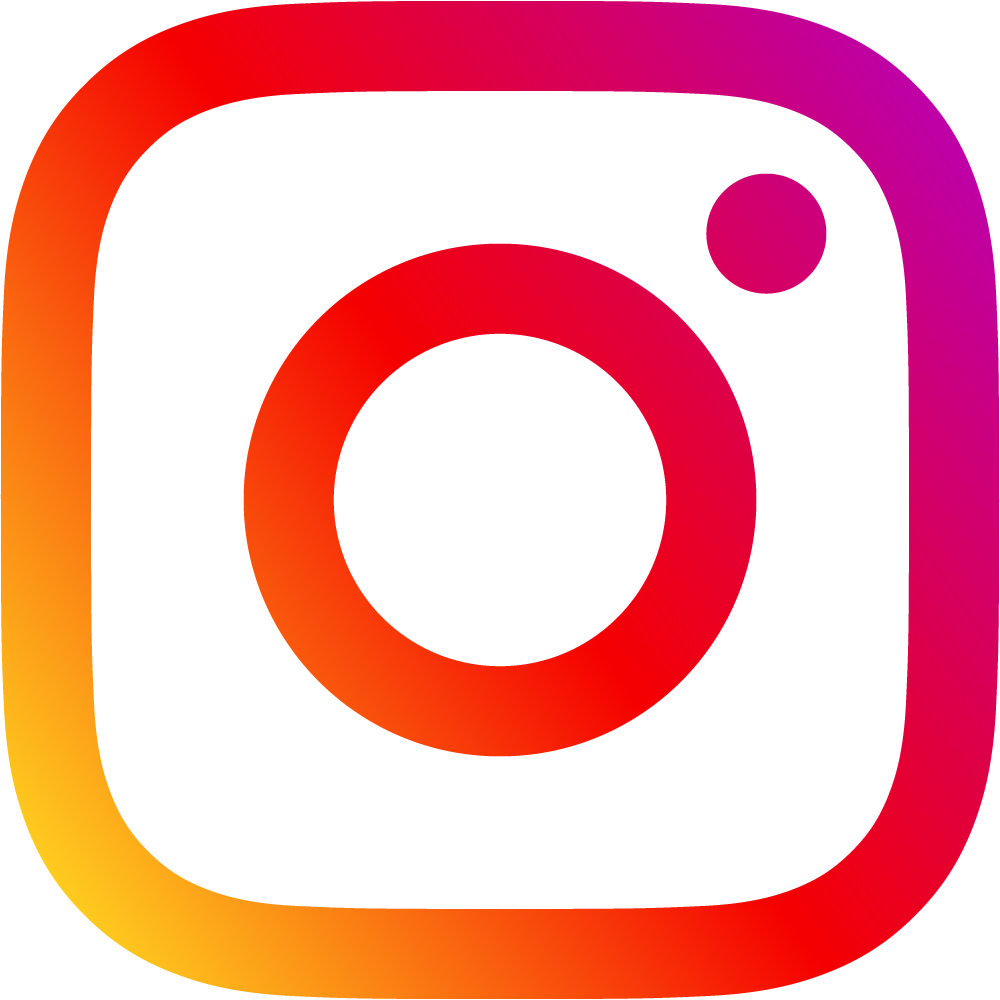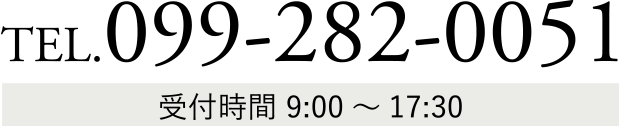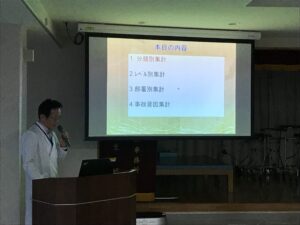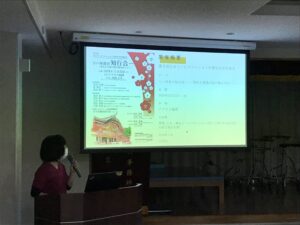「面会禁止」の一部解除のお知らせ(令和2年6月1日更新)
ご入院中の患者様並びにご家族の皆様には、当院の新型コロナウイルス感染予防対策にご協力頂きありがとうございます。
5月25日全国で緊急事態宣言が解除されたことを受け、感染対策委員会にて6月1日より『面会禁止』の一部解除となりましたので、お知らせいたします。
今後、近県及び全国の新型コロナウイルス感染者数の増加次第では、再度『面会禁止』となることがありますので、新型コロナウイルスの完全な収束までの期間は、ご入院中の患者様並びにご家族の皆様には引き続きご迷惑をお掛け致しますが、ご理解、ご協力いただきますようお願い致します。
令和2年6月1日
田上記念病院 院長
面会時の注意事項
面会可能な方はご家族のみとし、1回の面会で2名までと致します。但し、県外からの来訪者(2 週間以内)、2 週間以内に県外来訪者との接触の可能性のある方は面会禁止といたします。
同時に全病棟内でご面会できる総人数は20名以内と致します。
検温時、37.0℃未満の方。
面会時間は、15分以内でお願い致します。
面会の際は、必ず手指消毒及びマスクの着用をお願い致します。
面会時間: 平日 12:00 ~ 14:00 / 17:00 ~ 19:30
土日祝日 12:00 ~ 14:00 / 17:00 ~ 18:30
骨密度測定装置を導入しました。
令和2年5月より、骨密度測定装置を導入しました。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
「医療設備」
https://tagamikinen-hp.jp/about/medical-facility/

骨密度測定装置の導入と同時に骨粗鬆症の診療を開始しています。
骨粗鬆症については、「整形外科」のページをご覧ください。
「整形外科」
http://www.shunpukai-hospital.com/department/orthopedic-surgery/
厚生労働省による要介護原因の調査では、「脳卒中」「老衰」に次いで「骨折・転倒」が第3位となっています。
寝たきりの大きな原因となる骨折は、骨がスカスカになってもろくなる『骨粗鬆症』が主な原因であり、早期の治療と予防によって骨折のリスクを下げることができます。
過去に骨折をしたことがある、背中や腰に痛みがある、若いころに比べ身長が低くなったなどあれば『骨粗鬆症』の疑いがあります。
また、女性は加齢による女性ホルモンの減少により骨粗鬆症になる危険性が高いため注意が必要です。
上記以外にも様々な要因はありますが、骨粗鬆症について気になる方は当院に一度ご相談ください。
リスクマネジメント委員会及びNST委員会合同全体研修会を行いました。
令和2年1月31日(金)17:45より、リスクマネジメント委員会及びNST委員会合同全体研修会を行いました。
各委員会の発表内容は、以下の通りです。
リスクマネジメント委員会「令和1年事故報告統計の総括」
リスクマネジメント委員長の亀澤医師より、インシデント及びアクシデントの件数報告及び報告内容の分析報告がありました。
病院内で事故がどこでどのように、どんな時に何が原因で起こるのかが細かく分析されていました。
この結果をもとに今後の事故防止に努めていきます。
続いて、
NST委員会「第9回 日本リハビリテーション・栄養学会学術集会 研修会参加報告」
学会に参加した辻看護師より報告がありました。
廃用症候群でリハビリテーションを行っている入院高齢者の約9割が低栄養を認めており、回復期リハ病棟では、入院時に約4割の患者が低栄養状態であると報告されています。
通常であれば、積極的なリハビリを行うことで摂取したたんぱく質が筋肉の合成に利用され筋力UPが見込まれます。しかし、低栄養状態でリハビリを行うとエネルギーが不足しているため筋肉を分解してエネルギーを得ようとします。結果、筋力が減少することになります。
加齢に伴う進行性かつ全身性の筋肉量と、筋力の減少により身体機能の低下が起こることをサルコペニアと呼びますが、病院での不適切な安静や禁食によっておこるサルコペニアを「医原性サルコペニア」と呼びます。
「医原性サルコペニア」を出さないために「リハ栄養」の考え方を医療従事者が学び、多職種で患者様の栄養をみれば、より良い栄養管理と効果的なリハビリが行えるため患者様の状態回復に大きく貢献できると話がありました。
文責 前田